|
安倍首相が執念を燃やす集団的自衛権の議論が佳境に入りつつある。3月31日には、安倍の前のめりの発言に異論が起こった与党自民党に対し、説得を任された高村正彦自民党副総裁が「国の平和を守るためには、平和外交努力と抑止力が必要」、「砂川裁判の最高裁判決でも必要な自衛権行使は当然、と出ている」などと言って自民党内の議論を鎮静化させたという。 
昭和34年の砂川裁判の援用については、裁判を曲解したご都合解釈(朝日4/6)とか、論拠は暴論(毎日4/17)と批判されているが、安倍はこの他にも国際情勢の変化(近隣諸国との緊張)から、憲法25条で定めた国民の「生存権」確保にいたるまで、手当たり次第に牽強付会の理屈を持ち出している。憲法25条とはご存知のように「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」というもので、これがなぜ集団的自衛権になるのか。今や彼の頭の中は、すべてが集団的自衛権に結びついているとしか思えない。
◆「平和外交努力と抑止力の2本柱」、その実体とは?
そもそも、高村が「国の平和を守るには、平和外交努力と抑止力(武力行使の備え)が必要」と言い、「だから抑止力としての集団的自衛権が必要」と言うのは、もっともらしく聞こえるが、これが曲者。実態を見れば安倍政権がそんな事を言う資格がないないことが分かる。何しろ平和外交努力は疎かにしながら、抑止力の方だけは安全保障の権限を首相に集中する「国家安全保障会議」の設置、それを機能させるための「特定秘密保護法」、国内防衛産業を育成する「武器輸出三原則の見直し」、そして現在の「集団的自衛権」と、矢継ぎ早に強化を目指して来た。
こうした一連の抑止力強化の理由として使われたのが国際情勢の変化、すなわち中国を念頭に置いた近隣諸国との緊張である。であるなら、外交努力で緊張を和らげるかと言えば、そうではない。安倍にとってはむしろ隣国との緊張が高まっている方が、念願の「強い国作り」がやりやすいと言うことになる。その結果、中国が先か日本が先かは議論が分かれるにせよ、互いに軍備を強化し緊張を高める「緊張の再生産」が生まれて行く。
 2012年12月の衆議院選挙の時に安倍は、第一次安倍内閣で中国との関係改善(戦略的互恵関係)を作った実績を持ちだし、「自分こそが関係改善の適役」と言っていたのに、それを忘れたかのように外交努力を軽視している。現在は完全に冷戦状態で、習近平からは靖国参拝の後、「歴史修正主義者」と敵視され日本包囲網を敷かれつつある。従って、高村が言うような「平和外交努力」と「抑止力」の2本柱で国を守るという主張は、安倍政権に限っては説得力を持たない。どうして高村の説得に自民党の大勢が言いくるめられてしまうのか、首をかしげたくなる。 2012年12月の衆議院選挙の時に安倍は、第一次安倍内閣で中国との関係改善(戦略的互恵関係)を作った実績を持ちだし、「自分こそが関係改善の適役」と言っていたのに、それを忘れたかのように外交努力を軽視している。現在は完全に冷戦状態で、習近平からは靖国参拝の後、「歴史修正主義者」と敵視され日本包囲網を敷かれつつある。従って、高村が言うような「平和外交努力」と「抑止力」の2本柱で国を守るという主張は、安倍政権に限っては説得力を持たない。どうして高村の説得に自民党の大勢が言いくるめられてしまうのか、首をかしげたくなる。
◆日本は「戦争が出来る国」に近付いているのか
こうした実体を見ると、安倍の防衛政策は、近年の国際情勢の変化を口実にはしているが、実はそれとは別ものなのではないか。むしろ、「強い国家を作る」という彼の年来の国家観に基づいた政策と見る方が当たっているかもしれない。もともと自民党右派は平和憲法を改正し、自力で国を守るという「防衛大国」を夢見て来た。今の安倍政権もその独自の国家像に向かって突き進んでいると見るべきだろう。
そして、集団的自衛権の先には、投票権を18歳に引き下げて憲法を変えやすくする「国民投票法の改正」(4月17日審議入り)、次に「憲法改正」が待っている。これをやり遂げるまで、安倍政権は何かと言えば国際情勢の変化や近隣諸国との緊張の高まりを口実にするだろう。その先にどんな国家体制が待っているか。それを考えることが、今回の「戦争が坂道を転がり出す時」というタイトルにもなって来るわけである。
つまり、明治以降4回も戦争を経験した戦前の軍事国家としての“ありよう(国家体制)”に比べて、今の日本はどこまで近づいているのか、ということである。戦後の日本は70年近く平和を享受して来て、自衛隊も含めて国民が「戦争で死ぬ」という経験も実感もない。平和慣れしていて、政治家も国民もリアリティーを持って戦争というものを考えていない。しかし、もし本当に9条を放棄して武力で国際的紛争を解決するために死者も出すとすれば、その先の日本にどういうことが待っているのか。私たちは、それを見極めるべき時に来ているのだと思う。
◆「戦争で勝てる国」を目指した戦前の国家体制との比較
戦前の大日本帝国は、明治維新から太平洋戦争が始まる73年の間に、「戦争が出来る国、戦争で勝てる国」を目指して来た。富国強兵をめざす明治憲法があり、軍国主義的、国家主義的な教育があり、治安維持法のような思想統制があり、検閲などのメディア統制もあった。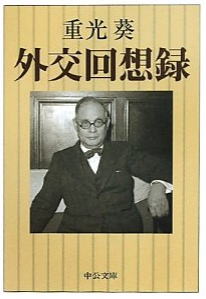 さらには、政党を解体して戦争遂行に当たる大政翼賛会があり、戦時に運命を共にする軍事同盟(三国同盟)があり、国のすべてを戦争につぎ込む国家総動員法もあった。 さらには、政党を解体して戦争遂行に当たる大政翼賛会があり、戦時に運命を共にする軍事同盟(三国同盟)があり、国のすべてを戦争につぎ込む国家総動員法もあった。
また、その根幹には戦争の道具として強制的に若者を集められる「徴兵制」があり、軍部が都合よく利用した天皇制があった。こうした軍事的体制を備えた国が、いったん戦争の坂道を転げ出した時には、それを止めることがいかに難しいか。それは例えば、開戦直前に戦争を止めるために一身をなげうって努力した外交官、重光葵(まもる)の「外交回想録」などを読むと、良く分かる。(重光葵については回を改めて書きたい)
問題は、いま安倍ら自民党右派の「強い国作り」によって進められている国家改造が、戦前日本の“ありよう”に比べてどうなのかと言うことである。坂道にすれば、まだ殆ど平地に過ぎないのか、それとも少しは坂道に差し掛かっているのか。安倍自身はそういうこと(軍国主義)は全く考えていないと言うだろうが、一連の防衛政策の急展開を見ていると、こういうトータルな視点から、安倍政権の取り組みを監視しておくことも必要ではないかと思えるのだ。
◆戦争のリアリティーのない国
安倍政権は「戦後レジームからの脱却」を掲げて、アメリカから押し付けられたとする現在の平和憲法を否定し「憲法を国民の手に取り戻す」と言う。教育を首長(政治家)の意向に沿わせるための制度改革を行い、美しい国への誇り教育や領土教育を強めようとしている。また、公共放送への人事介入を通してメディア操作も図ろうとしている。武器輸出や軍事技術の国際共同開発は、結果として軍需産業の発言力を強めるだろう。
天皇制について言えば、現在の天皇陛下はむしろ平和憲法の象徴のような存在であり(*)、今のままなら戦前のようなことにはならないだろう。しかし、自民党の憲法改正試案によれば、天皇を「元首」と表記する案になっており、そのことで彼らが何を意図しているのか、それも視野に入れておかなければならない。いったん作られた流れは(よほどの歯止めがない限り)政治家たちの意図を超えて拡大し始めるからだ。
*去年12月23日の誕生日の記者会見で天皇が平和憲法を評価し、遵守して行くとした発言部分をNHKが削除して放送したことが話題になっているくらいだ
こうして見ると、安倍の「強い国作り」も戦前の大日本帝国に比べれば、まだよちよち歩きの幼児程度で、そう神経をとがらす必要はないかもしれない。しかし、生まれて僅か一年ちょっとでここまで来たことを考えれば、まだ子供だと見くびるわけにはいかない。また、戦争のリアリティーのない国が実際に戦争で戦死者を出す事態になれば、今の日本で命を落とすために自衛隊に入る人は少ない筈だから、たちまち次の課題(徴兵制)が議論に上って来る。 そして徴兵国家になれば、日本は立派に(中国や韓国、ロシアが警戒する)軍事国家になる。 そして徴兵国家になれば、日本は立派に(中国や韓国、ロシアが警戒する)軍事国家になる。
集団的自衛権が、今の国際情勢の中で戦争に直結するのかどうかは別途研究すべきテーマである。しかし、一連の防衛政策の発想が、良く言われるように安倍の戦前回帰的な国家観に基づいているとすれば、書いて来たような大局的な(軍事国家への道筋としての)「戦争が坂道を転がり出す時」を視野に入れておくことも必要になって来ると思う。
|