|
�@���g���̖ҏ��������Ă���B���̏����������Q������łȂ��A�����͈Ӗ��̂��鎞�Ԃ��߂������ƁA���Ԃ͋ߏ��̎s�����2�K�́A�w�ǒN�����Ȃ��i���R�[�i�[�ɏo������B�₦�߂����[�ɔ����Ē��Y�{�����͂��A�������������āB�����ł̓Ǐ��ɂ��Ă͍Ō�ɐG���Ƃ��āA��������ŋ߁A�e���r�̃C���^�r���[�ɏo�����Ƃɂ��������Ă��������B�����́A���̏���������邽�߂ɗF�l��1���ő��Â̍����S���t�����s���������i7/26�j�̂��Ƃł���B���̓��́A�킪�z�J�s�̉ԉΑ��ł��������B�����ړ��Ăɖ���Ƃ�����ɂ���ė����B
���������Ɖԉ��������ETV���W������
�@�ԉ͖ڂ̑O�̗V���n��������オ��̂ŁA�w�ǐ^��ɏオ��ԉ̔��͂�2�l�̑������i8�A6�j�Ɗy���B���N�́A��N��萷��Ȋ������������L��ɂ��ƁA���悻90���̊Ԃ�5�甭���オ�����������B���ꂪ�I���ĉƑ��݂�Ȃ��Q���Ɉ����グ����11������A���̔ԑg���n�܂����B ETV���W�u�Y���ꂽ����ҁ`�g���g���X�g�@���̋L�^�`�v�Ƃ���1���Ԃ̔ԑg�ł���B��O�ɊJ������A��ɗ��R�̏��w�R�l��ΏۂɎg��ꂽ�u�g���g���X�g�v�Ƃ������Ǒ��e�����������B���ꂪ�̓��i��Ɋ̑��j�ɂƂǂ܂�A���ː����o��������B ETV���W�u�Y���ꂽ����ҁ`�g���g���X�g�@���̋L�^�`�v�Ƃ���1���Ԃ̔ԑg�ł���B��O�ɊJ������A��ɗ��R�̏��w�R�l��ΏۂɎg��ꂽ�u�g���g���X�g�v�Ƃ������Ǒ��e�����������B���ꂪ�̓��i��Ɋ̑��j�ɂƂǂ܂�A���ː����o��������B
�@���̎听���̃g���E���͔�������141���N�B���e�܂��g��ꂽ�R�l�▯�Ԑl�ȂǁA�����̐l�X���A�̓��ɗ��܂����g���E����������A���t�@���ɂ���Ċ̑�����������N�������B����́A�g�p���牽�\�N���o���Ă���Ƃ����̂ŁA���̑������������m�炳�ꂸ�A�⏞�����ꂸ�ɖS���Ȃ��Ă���B�ԑg�́A���̒����ƕ⏞�����̕��u���ꂽ�̂��A�����Ë@�ւ̖��ɔ����čs���B���Ă̊��҂̉��V���Ȏ��������@���Ȃ���̗͍삾�����Ǝv���B���́A���͎Ⴂ���ɂ��̖����Ȋw�h�L�������^���[�ԑg�Ŏ��グ�����Ƃ�����B48�N�O�̂��Ƃł���B
��48�N�O�̉Ȋw�h�L�������^���[�̐���҂Ƃ���
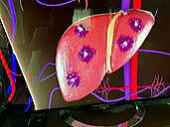 �@�����ւ̋L�^�u30�N��̃J���e�@�̓�����ҒǐՁv�Ƃ������g�i30���j�ŁA�����͂��܂�m���Ă��Ȃ������u�̓�����v�Ƃ������ɏœ_�Ă�ԑg�������B���N�A���̖��̒ǐՂɎ��g��ł����X���O�Y�����ƂƂ��ɁA�J���e�̒ǐՂ���ۂ̊��҂̃C���^�r���[�A�g���E�����ǂ̂悤�ɑ̓��Ɏ�荞�܂�邩�̎����Ȃǂō\���������̂ł���B���̔ԑg�̐���҂Ƃ��āAETV���W��I�f�B���N�^�[���瓖���̗l�q�ɂ��ĕ������ė~�����ƌ���ꂽ�̂�5���������B���ꂩ��1�����o����6���ɁA����߂��݂̑��X�^�W�I�ŃC���^�r���[���s��ꂽ�B �@�����ւ̋L�^�u30�N��̃J���e�@�̓�����ҒǐՁv�Ƃ������g�i30���j�ŁA�����͂��܂�m���Ă��Ȃ������u�̓�����v�Ƃ������ɏœ_�Ă�ԑg�������B���N�A���̖��̒ǐՂɎ��g��ł����X���O�Y�����ƂƂ��ɁA�J���e�̒ǐՂ���ۂ̊��҂̃C���^�r���[�A�g���E�����ǂ̂悤�ɑ̓��Ɏ�荞�܂�邩�̎����Ȃǂō\���������̂ł���B���̔ԑg�̐���҂Ƃ��āAETV���W��I�f�B���N�^�[���瓖���̗l�q�ɂ��ĕ������ė~�����ƌ���ꂽ�̂�5���������B���ꂩ��1�����o����6���ɁA����߂��݂̑��X�^�W�I�ŃC���^�r���[���s��ꂽ�B
�@2���ԋ߂����C���^�r���[���ꂽ���A�f�B���N�^�[��I����̊S�́A�����Ë@�ւ����̖������̍��܂ŕ��u�����̂��Ƃ������ƂƓ����ɁA��������Ɏ��グ�����f�B�A�͂��̌㒷���ԁA���̒��ق����̂��Ƃ������ƂɌ������Ă����B�Ȃ��Ȃ������ɂ����e�[�}�ł͂��邪�A�����҂̈�l�Ƃ��ăC���^�r���[�ɉ����邱�Ƃɂ����BI����ɂ͍Ō���u�Ȃ������邱�ƂɌ��߂��̂ł����v�ƕ����ꂽ���A�����g�́A���N���̐��E�ł���ė����̂�����A���f�B�A�̐ӔC�Ƃ������A�����͕�d�̐��_�H�ŁA�ԑg����ɂ͋��͂��Ȃ���Ƃ����v���������B
�����f�B�A�̎����͂ɂ��Ă̎��̓���
�@�ԑg�́A���Ă̎��̔ԑg�����p���Ȃ���i��ōs�����B�ȉ��́A���̔ԑg�̒��قǂŃ��f�B�A�̐��i�I�Ȍ��E�ɂ��āA���Ȃ�ɓ��������e�ł���i�w�x�̕����j�B�u�������A�ꎞ����ɓ`���Ă������f�B�A�̕����ɂȂ��čs���܂����v�Ƃ����R�����g�ɑ����āB
�@�w�L���������f�B�A�̖����͂����Ɖʂ����ׂ���������������Ȃ��ł��ˁB�����Ǝ����I�ɂ��ׂ��������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�������ł���ˁB�����玟�ւƖ�肪�N���ė��Ă�������ƁB�����Ƒ傫�Ȓn�����g���̖��Ƃ��A���q�̖͂��Ƃ����̂�����ė����̂ŁB���������Ӗ��ł́A�ǂ����Œu���Y��ė����i�̂�������Ȃ��j�x�B
�@�u�ꎞ�����ꂽ�ɂ�������炸�A���N������Ă��܂����Ƃ����Ӗ��ł́A���������̃��f�B�A�̂��낳���������ł����ǁv��I����B
�@ �w�܂��A���f�B�A�Ƃ����̂͂����������̂ȂƎv���܂��ˁB���t���C���i�J��Ԃ��j�݂����Ȃ��Ƃ������ƌ����Ă��Ă��S�������Ă���Ȃ��B���̌�y��������ꌴ�����̂̂��ƁA�u�����g�_�E���v�V���[�Y�����[���Ƒ����Ă��邯�ǁA�����V�����Ƃ��A�ǂ������V�������g�݂�����Ƃ��A���������Ƃ��A���ꂪ���m�łȂ��ƁA��̃e�[�}�������Ǝ����I�Ɏ��グ�čs���̂͂Ȃ��Ȃ�����B�����͔߂������ȁA�����������Ƃ��Ǝv���B�����������ɂ��āA�u�Y����ė������v�Ƃ����̂́A�����ς������Ȃ����ȁx�B �w�܂��A���f�B�A�Ƃ����̂͂����������̂ȂƎv���܂��ˁB���t���C���i�J��Ԃ��j�݂����Ȃ��Ƃ������ƌ����Ă��Ă��S�������Ă���Ȃ��B���̌�y��������ꌴ�����̂̂��ƁA�u�����g�_�E���v�V���[�Y�����[���Ƒ����Ă��邯�ǁA�����V�����Ƃ��A�ǂ������V�������g�݂�����Ƃ��A���������Ƃ��A���ꂪ���m�łȂ��ƁA��̃e�[�}�������Ǝ����I�Ɏ��グ�čs���̂͂Ȃ��Ȃ�����B�����͔߂������ȁA�����������Ƃ��Ǝv���B�����������ɂ��āA�u�Y����ė������v�Ƃ����̂́A�����ς������Ȃ����ȁx�B
���l�X�Ȗ��łƂ���Nj��̎�����
�@���̌�A���������ɂ�����̖���A�g���E���ȊO�̓�������Ȃǂɂ��āA�C�O�̎���̏Љ�Ȃǂ��������ԑg�̏I���̕��ŁAI����u�g���g���X�g�̖�肪������Ă��܂������Ƃ��l�������ɁA���ꂾ���J��Ԃ�������Ȃ���A�Y��Ă��܂��͉̂��̂Ȃ̂��v�Ǝ��₳�ꂽ�B
�@�w�l�Ԃ͖Y����ۂ���ł��B�����Đ��80�N�ł��傤�B�L���A����ŏĂ��쌴�ɂȂ�Ƃ��ˁA�����������̂��������Ƃ����{�ŋN���Ă����A�����������Ƃ��F�A������ƖY��Ă��邶��Ȃ��ł����B�ǂ�ǂ�Y��Ă���B����������ς�A�l�Ԃ̔߂����Ƃ���ł��ˁB�i�h������j����Ă����ł���B�u���̂��ƁA�ǂ�����v�Ɓx�B
�@��ނ������|����ꂽ�Ƃ��A�������ǂ��������������Ŕԑg����낤�Ƃ����̂�����������Y��Ă����B�܂��A���̌�A���̃��f�B�A�����Ɏ��グ�����Ƃ��Q�҂�����3���l�ɂ̂ڂ邱�Ƃ����߂Ēm�����B���Ƃ��ẮA�u�̓�����v�Ƃ������̂̋��낵����`���邱�ƂŁA�Ȋw�ԑg�Ƃ��Ă̖ړI�͉ʂ������Ǝv���Ă����̂����m��Ȃ��B����A��ނ���ɍۂ��A������{���T���Ă݂�����������Ȃ��B�����ŁA���Ă̔ԑg�𑗂��Ė���Ă悤�₭�L������݂��������B�����ł����̂��Ȃ��A���Ȃ肵������ƍ���Ă����̂ň��S�����B
���N�ɂ��`���Ȃ���������
�@�����A������20�N�قǂ��āA���̐X���O�Y���������x�ԑg�����Ȃ����ƌ���ꂽ���Ƃ͑N���Ɋo���Ă���B���̎��́A���ɔԑg�̌���𗣂�Ă����̂œ���Ɠ������L��������B��ނȂ����Ƃł͂��������A���҂̗���ɗ��ĂA�������������Ă͒N�����ǂ����Ő����グ�����邱�Ƃ��A�܂��厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B��{�I�ɂ͓����҂����A��Q�ɐӔC���������Î҂Ȃǂ̖��ł͂��邪�A����Ƀ��f�B�A���ǂ̂悤�Ɋւ���čs���̂��B�Nj����ׂ��e�[�}�ł͂���Ǝv�����A�����₤���Ƃ͑��A���g�ɒ��˕Ԃ��Ă�����ɂ��Ȃ�B
�@�Ƃ������ƂŁA���̌��ɂ��ẮA�����悤�Ȃ��Ƃł��Ȃ��̂ŁA�J�~����ȊO�ɂ͒N�ɂ��`���Ȃ��ł����B�������A�����㉽�l���̒m�l����u�o�Ă����̂łт����肵�܂����v�Ƃ����A�����������B�����A���������A��Ƃ����̂ŁA�C���^�r���[�̃p�[�g������^��Ō����Ă�����B�u���������̊�A�V�~���炯���ˁB�h�[�����ł��h���ĖႦ�Ηǂ������̂Ɂv�Ƃ����̂����̊��z�������B�܂��A80�ɂ��Ȃ�Ή������邱�Ƃ͂Ȃ��B�������Ƃ��A�������Ƃ��~�߂ĒW�X�Ɛ����čs�������Ȃ��B

���Ō�Ɏ֑��Ȃ���̋ߋ���
�@�Ǐ��ɂ��ẮA�f��ē̗F�l���u����ǂ����낤�v�ƌ����啔�̎��㏬����ǔj�����B����ɁA�������]�[�ǂœ|�ꂽ�Ɖu�w�҂̑��c�x�Y�ƎЉ�w�҂̒ߌ��a�q�̉������ȁu�琁v�B���̂��̉��[���ƁA�iAI���]���h���I�ȁj�����̐i���ɂ��Ă̐[���l�@���������B���Ă������G�̏C����������i�g�b�v�ʼn��̍����j�B�������A���̃r�t�H�A�A�A�t�^�[�́u�ԈႢ�T��������v�Ȃǂƌ����Ă���B
|