|
11月12日の日本記者クラブの会見で、 小泉元首相が脱原発(彼はこれを原発ゼロという)について「決断すればできる」と言い、しかもその時期は「即ゼロ」と明快だった。上げ足をとられるような余計なことは一切言わず、敵の痛いところを突く言い方は相変わらず。「首相が決断すれば反対論者も黙る」、「原発ゼロの方針を出せば、必ず知恵のある人がいい案を出してくれる」、「(処分場は)10年以上かけて一つも見つけることが出来ない。政治の力で見つけると言うが、(そっちのほうが)よっぽど楽観的で無責任」と迫力がある。言葉の一つ一つが政治的に計算されている。 小泉元首相が脱原発(彼はこれを原発ゼロという)について「決断すればできる」と言い、しかもその時期は「即ゼロ」と明快だった。上げ足をとられるような余計なことは一切言わず、敵の痛いところを突く言い方は相変わらず。「首相が決断すれば反対論者も黙る」、「原発ゼロの方針を出せば、必ず知恵のある人がいい案を出してくれる」、「(処分場は)10年以上かけて一つも見つけることが出来ない。政治の力で見つけると言うが、(そっちのほうが)よっぽど楽観的で無責任」と迫力がある。言葉の一つ一つが政治的に計算されている。
やはりうまいと思うのは、原発の代わりになる自然エネルギーの開発を、「自然を資源にする事業は、壮大で夢のある事業だ」と、夢として描いたことである。そして、返す刀で「それに力をふるえる。こんな運のいい首相はいない」、「これは結局、総理の判断力、洞察力の問題だと思う」と安倍を挑発した。
彼の原発ゼロ宣言が、どういう勝算のもとに言いだされたのか、詳しいことは分からない。しかし、始まったのは(安倍政権やアメリカを核とした)原子力共同体との熾烈な戦いである。相手も必死で、すでに裏では右派雑誌やイエロー・ジャーナリズムを動員した、えげつない「小泉叩き」が始まっている。カネも相当動いているに違いない。
この原発ゼロ宣言がこれからどう発展するのか、或いは一場の夢で終わるのか。今、小泉の姿は単身で巨大な原子力ムラに立ち向かうドン・キホーテを思わせるところがある。ただし、失敗すれば脱原発の世論にも大きな影響を及ぼすだろうし、その行方は予断を許さない。従って、小泉の投じた波紋の行方と意味については、もう少し時間をかけてじっくり考えるとして、今回はすこし脇道にそれて別なテーマを書いて見たい。それは、図らずも小泉も掲げた(時代の)「夢」に関連することである。
◆「プロジェクトX」、誕生の経緯
原発ゼロを達成するために新エネルギーを開発する事業は壮大な夢だと、小泉は言った。人間集団が何かに挑戦する時は、使命感もさることながらチームの力をまとめる「大きな夢」が必要になることを、小泉は良く分かっている。そのことは、チーム全員がこの2年以上も「東北の被災地に優勝と言う喜びを与えたい」という夢を持ち続けて闘った東北楽天を見ても分かる。日本シリーズ優勝の時、「楽天と巨人では背負っているものが違うよ」と娘がいみじくも言っていたが、そういうことである。
夢があり、その夢に向かってチーム全員が力を合わせる。。。もう14年前になるが、私が企画に関って生まれたNHKの番組「プロジェクトX」も、そうした時代の夢を描いたシリーズだった。番組誕生のきっかけは2000年の番組改訂で、それまで夜の9時台にあったニュース番組が10時台に移り、その空いた夜9時台に「骨太の番組を並べる」という編成方針が打ち出されたことだった。
当時、番組部門の責任者の一人だった私は、「これは各セクション(部)の議論に任されていた従来のやり方では無理だろう」と思い、組織横断的な「番組開発プロジェクト」を作って、そこで企画を議論することにした。各部から選りすぐりのプロデューサーを集め、彼らが持ち寄る企画アイデアをもとに、私が座長になって毎週のように議論を重ねて行った。
その中の一つが「プロジェクトX」となった経緯はこうである。議論も大分煮詰まっていたある時、「以前に、こういう企画を考えたのだが」と出された企画がある。それは「グレート・チャレンジ」というタイトルのアポロ13号の冒険を描くドキュメンタリー・シリーズの企画だった。定時番組の提案ではなかったが、私たちはその「グレート・チャレンジ」というタイトルに飛び付いた。こんな挑戦モノが日本を舞台にして出来ないか、それも戦後の挑戦を……戦後の社会的事象をいろいろ集め、会議で議論する日が続いた。
そんなある日、私の頭に一つのアイデアが浮かんだ。「これらは、みんなチームでやっているよな。それに戦後は“プロジェクトの時代”と言われているじゃないか」。プロジェクトで成し遂げられた戦後の挑戦、しかも主役は無名のチーム全員。定時番組に耐えるかどうか、戦後の年表を眺めながら、「これは入る、これは入らない」という番組コンセプトを固める検討が行われた。これなら、何年間かは行けるなあということで、1999年の夏に編成に提案。タイトルは最初「ザ・プロジェクト」だった。
◆時代の夢を描いた「プロジェクトX」
その後、編成とのやり取りがあって、タイトルは「プロジェクトX~挑戦者たち~」になった。最初の「グレート・チャレンジ」は、サブタイトルに僅かに残ることになったわけである。番組は私の手を離れて提案部のIプロデューサーたちのもとで見事な番組に仕立てられて行った。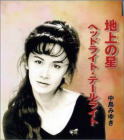 2000年3月28日に一回目の放送が始まって半年が経った頃、制作体制のやりくりに悩んでいたIプロデューサーと食事をしながら「この番組は絶対社会現象になるよ」と励ました記憶がある。 2000年3月28日に一回目の放送が始まって半年が経った頃、制作体制のやりくりに悩んでいたIプロデューサーと食事をしながら「この番組は絶対社会現象になるよ」と励ました記憶がある。
それから半年もたたないうちに、「プロジェクトX」はNHKの名物番組になり、中島みゆきの主題歌「地上の星」とともに文字通り社会現象になった。番組が描いたのは、戦後の日本が敗戦の傷跡から立ち上がり、高度経済成長に向けてひた走った「時代の夢」だろう。特に2回目の「窓際族が世界企画を作った VHS執念の逆転劇」(VHSビデオテープレコーダー、日本ビクター)は、私も試写室で泣けて来たが、日本の技術者の夢と挑戦を描く典型となった。
私は番組の当初から、「3年が花。3年でやめられたら満点」と言っていたが、あまりの評判の良さで上層部がやめるのを許さず、結局5年続いて後半にはスタッフはいろいろ苦い思いも味わうことになったらしい。しかし今、5年間の放送記録を眺めると、「プロジェクトX」は確かに、日本全体が明日の可能性に向けて夢を追い続けていた時代の物語だったと思う。見ながら毎回、「日本人も棄てたものじゃない」という感慨を引き起こしてくれる番組だった。
◆再び「時代の夢」を描けるか
「プロジェクトX」が描いた戦後の時代から、多くの年月が流れた。その後の日本は、バブルが崩壊し、失われた20年が来て、今やデフレ現象に喘いでいる。容易に時代の夢を描けない中にいる。去年以来のアベノミクスが、このデフレ退治を行うと言って、異次元の金融緩和を行っているが、その成果は日本のモノづくりの強化に少しは役立っているのだろうか。
株価の上昇と円安で、ソニーを除く日本の電機メーカーも一息ついているようだが、かつて時代を画したしたような新機軸の製品が日本のモノづくりメーカーから生まれたとは聞かない。リーマンショックなどで企業が委縮し、かつてのような「リスクを恐れないチャレンジ精神」が見られなくなったのが原因だと専門家は言うが、どうなのだろう。
日本は、再び時代の夢を描けるか。 新しい「プロジェクトX」は作れるか。私は定年後、ある独立行政法人で「サイエンスニュース」という5分の動画のインターネット放送に関っている。この2年で150本ほどのニュースを出したが、この日本でも基礎的な所では人類の未来を切り拓くような様々な先端的研究が行われていることが分かる。 新しい「プロジェクトX」は作れるか。私は定年後、ある独立行政法人で「サイエンスニュース」という5分の動画のインターネット放送に関っている。この2年で150本ほどのニュースを出したが、この日本でも基礎的な所では人類の未来を切り拓くような様々な先端的研究が行われていることが分かる。
例えば、エネルギー関連だけでも、「CO2ゼロを目指す石炭ガス化発電」、「浮体型の巨大風力発電」、「地熱利用の岩体発電」、「潮流を利用する海洋発電」、「海底下メタンとCO2の海中貯蔵」などなど。それに国際協力で進んでいる「核融合」研究もある。それから考えると、薬のネット販売などのアベノミクスの成長戦略も小さすぎて、夢がない。むしろ、原発ゼロを掲げて国を挙げて新エネルギーの開発に取り組むべきだとする小泉の意見の方が、夢があると言えないだろうか。
|