|
�@�C���^�[�l�b�g�����{�ɕ��y���n�߂�25�N�قǑO�A���͐��E���C���^�[�l�b�g���ƁiIT��Ɓj�����̂悤�ɋ���ɂȂ��Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ȃ��z���ł��Ȃ������B���ɃC���^�[�l�b�g�Y�Ƃ�����ɂȂ��Ă��A�]���̎Y�Ƃ��l�b�g�ɒu�������邾���ł͂Ȃ����ƁA�u�R���傫�ȃC�m�V�V�͏o�Ȃ��v�Ȃǂƌ������肵���L��������B�������A�������̂悤�ɁA�C���^�[�l�b�g�͎Љ��Y�Ƃ̂���������ꂩ��ς��A�d���̎d�����ς��A�����o�ϋK�͂��̂��̂��g�傳����傫�Ȍ����͂ƂȂ����B�C���^�[�l�b�g�͎R���傫�ȃC�m�V�V�ɂȂ����̂ł���B
�@�������͂���ł��A����ɒx��܂��Ƃ��ĕ���70���N�L�O���Ƃ̈�Ƃ��āA�C���^�[�l�b�g���g����NHK���̎��݁uNHK�{�����e�B�A�l�b�g�v�𗧂��グ����i1995�N�j�A�����Ƃ��Ă͂��Ȃ�ӗ~�I�ȃC���^�[�l�b�g���������Ė�����ɒ�Ă����肵���i2000�N�j�B�������A�ŋ߂�NHK�̃l�b�g�����z�M�Ɠ����ŁA���̎���������V���Ɂu���ƈ����v��u��剻�v�Ƃ������R�Ŕ�����ڍ������i��1�j�B����ɂ�����������ăl�b�g�i�o�ɔ��������f�B�A�́A���ǂ͎���ɏ��x�ꂽ�킯�����A���̌X���͑��̎Y�Ƃł������������B
�@ ���̊ԂɁA�V����GAFA�i�O�[�O���A�A�b�v���A�t�F�C�X�u�b�N�A�A�}�]���j�������̋��X�ɐZ�����A��炵��傫���ς���܂łɋ��剻�����B����S���E�̐l�X���X�}�z���g���A�O�[�O���̌����G���W�����g���Ē��ו������AFB��C���X�^�O�����Œ��ԂƂȂ���A�l�b�g������j���[�X��L����`���A�~�������̂�����A�}�]���Œ�������BGAFA�̓��f�B�A�����łȂ��A�����̏����ƁA�L���ƁAIT���i�̐����ƂȂǂ����ꂩ��h���Ԃ��ė����B���̐�A���̋���IT��Ƃ͂ǂ��Ɍ������̂��B�l�ނɍK���������炵�Ă����̂��낤���B ���̊ԂɁA�V����GAFA�i�O�[�O���A�A�b�v���A�t�F�C�X�u�b�N�A�A�}�]���j�������̋��X�ɐZ�����A��炵��傫���ς���܂łɋ��剻�����B����S���E�̐l�X���X�}�z���g���A�O�[�O���̌����G���W�����g���Ē��ו������AFB��C���X�^�O�����Œ��ԂƂȂ���A�l�b�g������j���[�X��L����`���A�~�������̂�����A�}�]���Œ�������BGAFA�̓��f�B�A�����łȂ��A�����̏����ƁA�L���ƁAIT���i�̐����ƂȂǂ����ꂩ��h���Ԃ��ė����B���̐�A���̋���IT��Ƃ͂ǂ��Ɍ������̂��B�l�ނɍK���������炵�Ă����̂��낤���B
���l�Ԃ̖{�\�ɑi���Ȃ���}��������GAFA
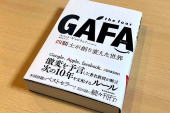 �@�uGAFA�`�l�R�m���n��ς������E�v�̒��ҁA�X�R�b�g�E�M�����E�F�C�iNY��w�����j�ɂ��AGAFA���l�Ԃ̖{�\�ɑi����`�Ő������Ă����B�Ⴆ�A�}�]���͂�葽���̂��̂��o���邾���y�ɏW�߂悤�Ƃ����X�̎�̏W�{�\�ɑi���A�A�b�v���́A�e�N�m���W�[��Ƃ��獂���u�����h�ɓ]�����邱�Ƃɂ���āA���̐��i�������Ƃ����I���͂����߂�Ƒi����B�O�[�O���͂��̖c��Ȓm���ʂɂ���Ď������̔]���O��茫���Ȃ����Ǝv�킹�AFB�͎��������҂Ɏ�����A������Ă���Ƃ�������ɑi����ƌ�������B �@�uGAFA�`�l�R�m���n��ς������E�v�̒��ҁA�X�R�b�g�E�M�����E�F�C�iNY��w�����j�ɂ��AGAFA���l�Ԃ̖{�\�ɑi����`�Ő������Ă����B�Ⴆ�A�}�]���͂�葽���̂��̂��o���邾���y�ɏW�߂悤�Ƃ����X�̎�̏W�{�\�ɑi���A�A�b�v���́A�e�N�m���W�[��Ƃ��獂���u�����h�ɓ]�����邱�Ƃɂ���āA���̐��i�������Ƃ����I���͂����߂�Ƒi����B�O�[�O���͂��̖c��Ȓm���ʂɂ���Ď������̔]���O��茫���Ȃ����Ǝv�킹�AFB�͎��������҂Ɏ�����A������Ă���Ƃ�������ɑi����ƌ�������B
�@���̌��ʁA�A�}�]���̓A�����J�ő�̏����Ƃɋ}�������A�n�Ǝ҃W�F�t�E�x�]�X�̎��Y�i14���~�j�͍��␢�E�����ł���BFB�͐��E��12���l�ɖ����g���A���E��20���l�������O�[�O���Ō������Ă���B���̊�Ɖ��l�͂ƂĂ��Ȃ��A���̎����]���z���A2017�N�ŃA�b�v����8000���h���i88���~�j�A�A���t�@�x�b�g�i�O�[�O���̐e��Ёj��5900���h���i65���~�j�A�A�}�]����4300���h���i47���~�j�AFB��4100���h���i45���~�j������B���{�ő�̃g���^�ł�25���~�i2020�N�j���B�������A�����̋����Ƃ͂���ɐ����𑱂��Ă���B
�����E���e��ڎw��GAFA
�@�A�}�]���̖�]�͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��B �P�Ȃ鏬���Ƃ����łȂ��A�E�F�u�T�[�r�X�iAWS�j�Ńl�b�g���g�����l�X�ȃr�W�l�X����A�h���[���A�q��@�A�C��A���ɂ��i�o���ĕ������x�z���A�f���h���}����ɂ����o���čő勉�̃��f�B�A���Y��L�����Ƃɂ��Ȃ낤�Ƃ��Ă���B�A�}�]���u�����h�̐��i�荞�݁A�ŋ߂ł͊e�n�̏����X�܂��������āA���������i�ɐG���X�܂����łȂ��A�z���̋��_�A�q�ɂɂ����Ă悤�Ƃ��Ă���B�O�ꂵ�����{�b�g���AAI�����i�߂Ă���B���̖ڎw���Ƃ���́A���v�����́u���E���e�v�ł���B �P�Ȃ鏬���Ƃ����łȂ��A�E�F�u�T�[�r�X�iAWS�j�Ńl�b�g���g�����l�X�ȃr�W�l�X����A�h���[���A�q��@�A�C��A���ɂ��i�o���ĕ������x�z���A�f���h���}����ɂ����o���čő勉�̃��f�B�A���Y��L�����Ƃɂ��Ȃ낤�Ƃ��Ă���B�A�}�]���u�����h�̐��i�荞�݁A�ŋ߂ł͊e�n�̏����X�܂��������āA���������i�ɐG���X�܂����łȂ��A�z���̋��_�A�q�ɂɂ����Ă悤�Ƃ��Ă���B�O�ꂵ�����{�b�g���AAI�����i�߂Ă���B���̖ڎw���Ƃ���́A���v�����́u���E���e�v�ł���B
�@FB���O�[�O���������悤�Ɋ֘A�ƊE�����Ȃ���A��苐�剻��ڎw���Ă��邪�A�ނ�̖�]���㉟�����Ă���̂����E������W�܂�L�x�Ȏ����ł���B���@�Ƃ����́A�ނ�̐��E���e�̕���Ɏ䂩��Ĕ���Ȏ����𓊓�����̂ŁA�����܂ł̊Ԃ͒Ⴂ�z���ł��䖝����Ƃ����AGAFA�ɂƂ��Ă͖��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���BGAFA�́A�������������̋����҂ƂȂ�\���̂����Ƃ́A���Ƃ��Ƃ��������邩�Ԃ��Ă����B�V�����x���`���[���炽�Ȃ����Ƃ��w�E����Ă���AGAFA�̓G��GAFA�������݂��Ȃ��ɂȂ��Ă���B�@
�����v�������̐�ɁA���O�������
�@����IT���GAFA�ɐ��e����悤�Ƃ��Ă��鐢�E�����A�����ɁA����ɂƂ��Ȃ��l�X�ȕ��Q���w�E����n�߂Ă���BGAFA�̗��v�����헪�ɂ���ď����ƁA�L���ƂȂNJ����̎Y�Ƃ����X�Ƌ쒀����čs�����ŁA�����̎��Ǝ҂����܂�Ă��邱�ƁB���̌��ʁA�����̒��ԑw���₹�ׂ�A�ŋ���[�߂Ȃ��ꈬ��̒��x�T�w�Ƒ命���̕n���w�Ƃ̊i�����܂��܂��J���Ă������ƁB�r�b�O�f�[�^����l�X�̊S�̌X����AI�i�l�H�m�\�j�����͂��邱�Ƃɂ���āA���h���I�ŋɒ[�ȃj���[�X�������悤�ɂȂ�A�����̕��f���i�ނ����Ȃǂł���B
�@�A�}�]����FB�A�O�[�O���͎��������̏�������肭�����悤�ɁA�c��Ȍl�f�[�^�i�r�b�O�f�[�^�j����O��I�Ȍڋq�������s���Ă����B����ɂ���Čl���^�[�Q�b�g�ɂ������ʓI�ȏ��i�L�����łĂ�悤�ɂȂ�A���i�̒҂��獂�������Ƃ�B���ꂪ����ł͌��O�ɂ��Ȃ���B�O�[�O���̌���������FB�ł̔��M���e����l�̌X���E�n�D���ۗ��ɂȂ�A���ꂪ�I���ȂǑ��̖ړI�ɗ��p���ꂩ�˂Ȃ����Ƃł���BFB�ł́A�u150��́g�����ˁh�ł��Ȃ��͊ۗ��ɂȂ�v�Ƃ��������邪�A���������l���̈����ɑ��鍑�Ƃ̋K���͎v���悤�ɐi��ł��Ȃ��B
�����ׂ������A�n�Ǝ҂̐��i�A�V�˂̎Ј�����
�@�l�X�Ȍ��O���w�E����Ă͂��邪�A GAFA���l����̂͗B��A���ׂ��̂��Ƃł����i�M�����E�F�C�����j�B��������R�ŁA�ނ�ɔ���ȃJ�l�𓊎�����l�����́A�����ꍂ�z�Ȍ��Ԃ�����҂��Ă���킯�ŁAGAFA���J���ҕی��A�i�Ď���p����������j���f�B�A�Ƃ��Ă̐ӔC�A�n��Y�Ƃ̕ی�Ȃǂɏ����ł������g�����Ƃ��������낤����B���ꂪ���{�̘_�����B�������n�Ǝ҂����͊�Ƃ̒��Ő�ΓI�Ȍ��͂�L���Ă���A�ނ���U���I�Ŏ��{��`�I�Ȑ��i��ς��邱�Ƃ͕s�\�B������FB�̃U�b�J�[�o�[�O���u���E�ōł��댯�Ȑl���v�Ƃ��������B GAFA���l����̂͗B��A���ׂ��̂��Ƃł����i�M�����E�F�C�����j�B��������R�ŁA�ނ�ɔ���ȃJ�l�𓊎�����l�����́A�����ꍂ�z�Ȍ��Ԃ�����҂��Ă���킯�ŁAGAFA���J���ҕی��A�i�Ď���p����������j���f�B�A�Ƃ��Ă̐ӔC�A�n��Y�Ƃ̕ی�Ȃǂɏ����ł������g�����Ƃ��������낤����B���ꂪ���{�̘_�����B�������n�Ǝ҂����͊�Ƃ̒��Ő�ΓI�Ȍ��͂�L���Ă���A�ނ���U���I�Ŏ��{��`�I�Ȑ��i��ς��邱�Ƃ͕s�\�B������FB�̃U�b�J�[�o�[�O���u���E�ōł��댯�Ȑl���v�Ƃ��������B
�@�ł́AGAFA�ɑ��鋐�l�����܂��\���͂���̂��B�����̃A���o�o�ȂǁA����̌��͋������Ă��邪�A���ꂼ��Ɍ��E������B�ނ���GAFA�̒��ŋ������������Ȃ��Ă������낤�ƌ����B���߂�1���h����ƂɒB������͋��炭�A�}�]���ł͂Ȃ����Ƃ��B�|���ē��{�̊�Ƃ��l����ƁAGAFA�͂͂邩�ޕ��ɍs���Ă��āA�ƂĂ��ǂ����͖̂����Ɍ�����B������AFB���O�[�O�����Ј��ɂ͓V�˂����̂�Ȃ����A���E������W�܂�O�[�O����6���l�̓V�����A���X���{�̘_���ɋ���ĐV���ȋ��ׂ��̃A�C�f�A������Ă���̂�����A�i���X�N����낤�Ƃ��Ȃ����{��Ƃ͂������j�N������ɒǂ������Ƃ͏o���Ȃ��B
������IT�K���B���͌��ʓI�Ȏ肪�łĂ邩
�@�ȏ�AGAFA�̐Z���͒P�ɐ������֗��ɂȂ����Ɗ��ł���������Ȃ��ʂ�����B�挎�A�R�`���ŗB��̕S�ݓX���|�Y���A190�l�̏]�ƈ������ق��ꂽ���A����Ȃǂ���ɂ̓l�b�g�ł̔������ȂǁA�w���`�Ԃ̕ω����e�����Ă���̂��낤�B���{�ł�EU�ɏK���āA�l���̈͂����݂�o�X���ւ̍����I�ȗv���ȂǂɊւ��āA�i�y�V���܂߂��j�K���̌������n�܂��Ă��邪�A�܂��͍������i12/18�����j�B���̐�A�e���͎��{�̘_���ɋÂ�ł܂�������IT��Ƃ��A�Љ�ɓK�������`�ɕς��čs����̂��B����ɂ��Ă͕ʓr�܂��l���čs�������B�@
��1�jNHK�����L�x�ȃR���e���c�����āA�A�N�Z�X���œ��{�ő�̃T�C�g��ڎw���Ƃ����āB��]����OK���������A������V���̒c�̂ł���V������甽����A�l�b�g�T�[�r�X�͔ԑg�̓I�ȍL��Ɍ��肷��Ƃ����A���������₩�ȈĂɂȂ����B
|