|
たまには目先を変えて、今の醜い政治の世界とは対極にある美しいものに触れたくなって、最近胸に響いた表現者やその芸術作品について書いてみることにした。「優しさと切なさと潔さと」と名付けた三題噺(ばなし)である。もっとも、(非力故に)その美しさに届かない内容になりそうな予感もする。ご容赦を。
◆石牟礼道子の優しさ
今年の2月10日、90歳で亡くなった作家の石牟礼道子さん。水俣の患者に寄り添い、その原因の水銀を垂れ流したチッソ水俣工場や本社への抗議行動の中心となり、さらに患者たちの心の叫びを「苦界浄土」3部作としてまとめ上げた。これ以上の苦しみがあろうかと思うような激烈な中毒症状の奧にある、患者家族の悲しみを患者たちの言葉で掬い取った希有な小説。石牟礼の表現世界はこれに止まらず、水俣地方の過去と現在、あの世とこの世の境、さらに水銀で汚染される前の不知火の豊穣の海、能の創作から歌の世界までに広がる。
その集大成は、献身的に彼女の執筆活動を支えた編集者で作家の渡辺京二をはじめとする様々な人々の努力によって17巻の全集となっているが、彼女の磁力に引きつけられるように集まった多くの心酔者に比べて、私などは足元にも及ばない読者である。15年以上も前に水俣に行き、現地の人たちと交流したことをきっかけに、東京での水俣展示や石牟礼の能「不知火」を観たりした。石牟礼が「たとえひとりになっても」と創刊号(1998年)に書いた患者たちの季刊誌「魂うつれ」もそれ以来、送って貰って来た。その最新号は「石牟礼道子追悼特集」である。
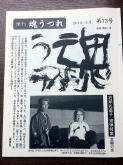
実に多くの人が石牟礼の思い出を語っているが、彼女に人生の指針を与えられた、優しさに励まされた、彼女とふれあうことは宝物以上の喜びだったと書いていて、感動を誘う。生前付き合いのあった瀬戸内寂聴も書いているが(朝日6/16)、石牟礼への追悼で埋め尽くされた新聞や雑誌を読んでは涙する事態になっている。特に編集者として彼女の才能に驚嘆し、以来50年にわたって彼女の側で文章を清書し、雑務から食事の世話までやってきた渡辺京二の「私は(石牟礼を)ずっとカワイソウニと思ってきた」と言う言葉を紹介している。
◆「悶(もだ)え神」になった道子
 評伝「石牟礼道子」(米本浩二)を読むと、石牟礼は幼少の頃、理不尽な扱いを受けて精神を病んだ祖母を世話しながら育ったという。幼心に、この世には圧倒的な理不尽があり、それはまた底知れぬ哀しみを生むことを胸に刻んで育った道子は、ずっと「この世に生まれてイヤだ」という虚無的な心の風景を抱え込んでいたらしく、思春期から結婚後の二十歳前後にかけて3回も自殺未遂を起こしている。その心が、水俣病の患者・家族の圧倒的哀しみに出会って「感応」した。水俣地方には人々の哀しみを自分のものとしてしまう「悶(もだ)え神」という存在がいるというが、まさに道子は水俣病に出会ってその「悶え神」になったのである。 評伝「石牟礼道子」(米本浩二)を読むと、石牟礼は幼少の頃、理不尽な扱いを受けて精神を病んだ祖母を世話しながら育ったという。幼心に、この世には圧倒的な理不尽があり、それはまた底知れぬ哀しみを生むことを胸に刻んで育った道子は、ずっと「この世に生まれてイヤだ」という虚無的な心の風景を抱え込んでいたらしく、思春期から結婚後の二十歳前後にかけて3回も自殺未遂を起こしている。その心が、水俣病の患者・家族の圧倒的哀しみに出会って「感応」した。水俣地方には人々の哀しみを自分のものとしてしまう「悶(もだ)え神」という存在がいるというが、まさに道子は水俣病に出会ってその「悶え神」になったのである。
「たとえひとりになっても」患者の側にたち、その運命を見届ける覚悟。それがチッソへの抗議行動の原点となり、後の彼女の底知れぬ優しさにつながっていく。その優しさに美智子妃も含めて多くの人々が、まるで磁石に引き寄せられるようにして集まった。その磁力の根底にあるのは、この世にある理不尽や絶望、そして圧倒的な哀しさを透徹した目で見届けた上でなお踏みとどまる優しさだと思う。まじめに生きている限り、人はその理不尽や哀しさを見ないわけにいかないのだ。それは(会津八一が救世観音を詠んだ)「あめつちにわれひとりゐてたつごときこのさびしさをきみはほほゑむ」を思わせる。
◆映画「万引き家族」を観る
話題の映画「万引き家族」を観た。題材は近年社会を賑わした様々な事件が下敷きになっている。親の死を隠して年金を貰い続けた話、親に虐待される子どもの話、 そしてこどもの誘拐。それらを用いてある血のつながらない家族を設定する。その昔、旦那を寝取られた老婆、その旦那が相手の女に生ませた娘の子(家出して一緒に住む)、殺人までして一緒になった男女。その夫婦が駐車場から盗んだ赤ん坊が大きくなった少年。そしてある冬の日に虐待親から外に出されて震えていた幼女の6人だ。それが一つ屋根のぼろ屋でその日暮らしをしている。 そしてこどもの誘拐。それらを用いてある血のつながらない家族を設定する。その昔、旦那を寝取られた老婆、その旦那が相手の女に生ませた娘の子(家出して一緒に住む)、殺人までして一緒になった男女。その夫婦が駐車場から盗んだ赤ん坊が大きくなった少年。そしてある冬の日に虐待親から外に出されて震えていた幼女の6人だ。それが一つ屋根のぼろ屋でその日暮らしをしている。
生活費は、老女の僅かな年金、男の日雇い賃金(すぐにケガをして働けなくなる)、クリーニング工場で働く女の賃金(まもなくリストラされてしまう)、風俗で働く家出娘、そして男と少年がタッグを組んで行う万引きである。やがて、その万引きに幼女も加わるようになる。その日常生活は奇妙なものだ。血のつながらない者たちが、肩を寄せ合って生きる。一見クールだが、互いを思いやる暖かいものも流れている。例えば、夏になって一家はまるで本物の家族のように海辺に水遊びに行く。そこで戯れる男と少年、女と幼女。その遠景を見つめる老女(樹木希林)の何とも言えない満ち足りた表情。本来なら社会の吹きだまりで絶望的な孤独にさらされるべき人々である。
◆是枝監督が描いた「切なさ」
ある朝老女は死ぬが、家族は遺体を家の風呂場の下に埋めて、年金を詐取することにする。ネタバレになるので詳しくは書けないが、やがて少年の万引きをきっかけにこの家族に破局が来る。夫婦のうち女は死体遺棄で捕まり、少年は施設に預けられ、幼女は元の虐待親に戻される。一人一人がバラバラになる過程で、女は婦警の尋問を受ける。なぜ一緒にいたのか。なぜ子どもを誘拐したのか。それほど子どもが欲しかったのか。その尋問は、いわば社会常識からの非難だが、その外側で暮らしてきた女も少年も当然のことながら説明する言葉を持たない。
 答える一人一人の顔のアップ。秀逸なのは安藤さくら演ずる女の演技である。「子どもを産んでいないのに親にはなれないよね」という婦警の陰の声に女の表情が次第に崩れ、じわじわと涙がにじんでくる。その演技に引き込まれる。カンヌで審査した女優たちが絶賛したという演技である。映画は施設に入った少年が男と一晩過ごして一緒に雪だるまを作るシーン、風俗で働いていた家出娘が今は誰も住んでいない家をそっとのぞきに来るシーン。虐待親に引き取られた幼女がベランダで一人、外をのぞいているシーンなどを積み重ねて終わる。 答える一人一人の顔のアップ。秀逸なのは安藤さくら演ずる女の演技である。「子どもを産んでいないのに親にはなれないよね」という婦警の陰の声に女の表情が次第に崩れ、じわじわと涙がにじんでくる。その演技に引き込まれる。カンヌで審査した女優たちが絶賛したという演技である。映画は施設に入った少年が男と一晩過ごして一緒に雪だるまを作るシーン、風俗で働いていた家出娘が今は誰も住んでいない家をそっとのぞきに来るシーン。虐待親に引き取られた幼女がベランダで一人、外をのぞいているシーンなどを積み重ねて終わる。
見終わって、それぞれの演技と自然なカメラワーク、シナリオの巧みさを噛みしめていると、突然、見終わった後の感情の適切な表現が浮かんできた。「切なさ」である。今は、5歳の女の子が「ゆるして」と書きながら親に殺される時代である。そうした人間の業と無明を見つつ、なおかつ生きることの「切なさ」。安藤さくらの表情の長回し、追い詰められた少年が高所からあっさりと飛び降りるシーンなどで監督が描きかったのは、この時代の圧倒的な不条理と虚無感、それを抱えて生きる庶民の「切なさ」への共感なのだろう。石牟礼に通じるものだ。
◆映画「峠」。河合継之助の潔さの重い意味
最後に。友人の映画監督がようやく製作に入ることになった。戊申戦争時の長岡藩の家老、河合継之助を描いた小説「峠」(司馬遼太郎)の映画化である。そこでは河合を“最後の侍(ラストサムライ)”として描くのも主要なテーマだとは思うが、私としては観客が(敗者の側からも歴史を見る)「歴史の目撃者、歴史の立会人になる」という要素もしっかり描き込んで欲しいと監督には伝えている。
小説のラストで、自分の遺骸を焼くための薪(たきぎ)の火を見つめる河合継之助の胸に去来するものを思うと、歴史の転換点の中で過酷な運命を選択せざるを得なかった河合の「潔さ」の重い意味が浮かび上がるようである。こうした滅び行く武士の潔さも、戦で苦しみを受ける民衆の切なさも、今の傲慢な政治家たちとは無縁のもので視野にも入っていないに違いない。出来上がりを楽しみにしている。
|