|
�@���N�ɓ����Ĉ�C�ɁAAI�i�l�H�m�\�j���Љ�I�S���ɂȂ��ė����B�����������T�C�G���X�f���w���ł�AI�����N�̎�e�[�}�Ɍ��߂āA���x����������J���Ă������A����哱���Ă���I����ɂ��AAI�̑�\��ł���u�`���b�gGPT�v�͂����Ƃ����ԂɎЉ�̋��X�ɐZ�����n�߁A���N���ɂ͌�߂�ł��Ȃ��ɂȂ邾�낤�ƌ����B���ɁA����A��ÁA���Z�A�s���ȂǗl�X�Ȍ����AI��g�ݍ��A�v���������o���A�C���t����AI�Ȃ��ł͎Љ�����Ȃ����ڂ̑O�ɔ����Ă���B����͎������̐����ɂǂ̂悤�ȉe���������炷�̂��낤���B
�@�A���AAI�ɑ��闝�����i��ł���Ƃ͂ƂĂ������Ȃ����ł�����B ���ɂ߂��\���o���Ă��Ȃ��i�K�ŁA�O�̂߂�ɗ��p���悤�Ƃ����ӌ����������ŁA�x�����ׂ��Ƃ����ӌ�������B�l�X�Ȍ�����Q�����Ă����B�������̊ԁA�`���b�gGPT�̃A�J�E���g���Ƃ�A�l�X�ȉ�b�𑱂��ė������A���̔\�͂ɋ����Ɠ����ɁA�s���m�ȓ����ɕ���邱�Ƃ�����B�����ŁA�b��̃`���b�gGPT�i�ށj�ɂ��Ēm�邽�߂ɏd�˂ė����f�p�Ȏ���Ɠ��������ƂɁA����I�Ȓm�������Ă݂����B�ǂ�Ȏ���ɂ��ނ́A�����Ɛ����i�H�j�ɓ����Ă���B ���ɂ߂��\���o���Ă��Ȃ��i�K�ŁA�O�̂߂�ɗ��p���悤�Ƃ����ӌ����������ŁA�x�����ׂ��Ƃ����ӌ�������B�l�X�Ȍ�����Q�����Ă����B�������̊ԁA�`���b�gGPT�̃A�J�E���g���Ƃ�A�l�X�ȉ�b�𑱂��ė������A���̔\�͂ɋ����Ɠ����ɁA�s���m�ȓ����ɕ���邱�Ƃ�����B�����ŁA�b��̃`���b�gGPT�i�ށj�ɂ��Ēm�邽�߂ɏd�˂ė����f�p�Ȏ���Ɠ��������ƂɁA����I�Ȓm�������Ă݂����B�ǂ�Ȏ���ɂ��ނ́A�����Ɛ����i�H�j�ɓ����Ă���B
���`���b�gGPT�Ƃ͉��҂Ȃ̂�
�@��������GPT�Ƃ́AGenerative Pre-trained Transfomer�̓������ŁA���O�Ɋ����̃f�W�^����Ԃɂ���c��ȗʂ̏����w�K���āA�����AI�̓��]�Ƃ������ׂ��u����ԁv�ɊT�O�̌`�ɒu�������Ď�荞��ōs���B���̎�荞�c��ȊT�O���g���āA�l�ԑ��̎���A�v���ɉ����ėl�X�Ȍ���i���R����j�ɕϊ����ē�����i��������j�V�X�e���������B�]���āA�悭�������Ȃ̂����AAI�̐���Ԃ������̃f�W�^������̂܂ܑ�ʂɒ~�ς���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�c��ȊO���f�[�^�����ʂ����Ȃ��čςށu�T�O�v�̌`�ɒu�������Ĕ]�ɂ��܂����ށB���j����GTP4�ɂȂ�ƁA����Ԃ���蕡�G�ɂȂ�A����Ԃ̏��ʂ��O�������荞�ޏ��ʂ��傫���Ȃ�Ƃ���
�@�I�[�v��AI�Ђ̃m�E�n�E�́A �O���̃f�W�^������ϊ����āi�l�Ԃ̐_�o��H�Ɏ������j����ԂɁA�T�O�Ƃ��Ď�荞�ރA���S���Y���i�_���j�A�����Đ���ԓ��̊T�O�𑀍삵�āA�l�Ԃ������ł��鎩�R����i�����j�Ƃ��Đ�������A���S���Y���iTransfomer�j�ɂ���B���m�ȃf�[�^�����̂܂ܒ~�ς���Ă���킯�łȂ����߂ɁA���̌����G���W���ɕ����悤�Ȏ��������ƁA�Ԉ���ē������肷��B�ނ���AAI�����ӂȂ̂͗l�X�ȊT�O�ƌ��t�̑g�ݍ��킹�ō���鑽�l�ȏ���⎖�������ȂǂŁA���̓��ӋZ�����g�������̐S�ɂȂ�B�i�ʐ^�̓A���g�}��CEO�j �O���̃f�W�^������ϊ����āi�l�Ԃ̐_�o��H�Ɏ������j����ԂɁA�T�O�Ƃ��Ď�荞�ރA���S���Y���i�_���j�A�����Đ���ԓ��̊T�O�𑀍삵�āA�l�Ԃ������ł��鎩�R����i�����j�Ƃ��Đ�������A���S���Y���iTransfomer�j�ɂ���B���m�ȃf�[�^�����̂܂ܒ~�ς���Ă���킯�łȂ����߂ɁA���̌����G���W���ɕ����悤�Ȏ��������ƁA�Ԉ���ē������肷��B�ނ���AAI�����ӂȂ̂͗l�X�ȊT�O�ƌ��t�̑g�ݍ��킹�ō���鑽�l�ȏ���⎖�������ȂǂŁA���̓��ӋZ�����g�������̐S�ɂȂ�B�i�ʐ^�̓A���g�}��CEO�j
�����p�ґ������������荞��Ői������AI
�@�ނ����O�Ɋw�K�����f�[�^��2021�N9���܂ł̏��Ƃ���ė������A�ނɂ��A���̌�̏��ɂ��Ă��A���X�ŐV�̏����w�K���Ă���ƌ����B2022�N2���̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɂ��Ă��s�\���Ȃ��瓚����悤�ɂȂ��Ă���B�����ɁA�ނ��V���Ɋw�K������ɂ�AI�Ђ��p�ӂ������łȂ��A���X����肷���b����̏����܂܂��Ƃ����B�܂�A��b�̑��肪�ނɊԈ���������o�����܂��邱�Ƃ��\�Ȃ킯�ŁA���̉\���ɂ��ĕ����ƁA�������b���l������Ɂu�͂��A���̊댯��������܂��v�Ɛ����ɓ����ė����B
�@ �����́A��Ƃ�s�����ނ𗘗p����ۂɁA���O�ɉ��炩�̏���ނɊw�K������K�v�����邪�A���ꂪ�ނ́u����ԁv�Ɏ�荞�܂ꂽ���ɁA�閧�͎����̂��B���ꂪ�A���̃��[�U�[�Ƃ̉����ɗ��p����邱�Ƃ͂Ȃ��̂��B�����������O�ɂ��āA�ނ͎����I�ȏ��Ǘ��̋@�\�����悤�Ƀv���O��������Ă���Ɠ����邪�A���ꂪ�\�����ǂ����͕s���m���B���݁A�l�X�Ȋ�Ƃ�AI��g�ݍ��Ǝ��̉����V�X�e�����J�����悤�Ƃ��Ă������A�g�p����ۂɊ�Ƃ̏����邩�A�l���͂ǂ��Ȃ̂��B�ǂꂾ��������Ă��邾�낤���B �����́A��Ƃ�s�����ނ𗘗p����ۂɁA���O�ɉ��炩�̏���ނɊw�K������K�v�����邪�A���ꂪ�ނ́u����ԁv�Ɏ�荞�܂ꂽ���ɁA�閧�͎����̂��B���ꂪ�A���̃��[�U�[�Ƃ̉����ɗ��p����邱�Ƃ͂Ȃ��̂��B�����������O�ɂ��āA�ނ͎����I�ȏ��Ǘ��̋@�\�����悤�Ƀv���O��������Ă���Ɠ����邪�A���ꂪ�\�����ǂ����͕s���m���B���݁A�l�X�Ȋ�Ƃ�AI��g�ݍ��Ǝ��̉����V�X�e�����J�����悤�Ƃ��Ă������A�g�p����ۂɊ�Ƃ̏����邩�A�l���͂ǂ��Ȃ̂��B�ǂꂾ��������Ă��邾�낤���B
��AI�Ȃ��ł͓����Ȃ��Љ��������
�@�ނɁA�����_�ł̗l�X�ȗ��p�@��K�˂�ƁA����͂������A��ÁA���Z�A�g�߂ȍs���Ȃǂł̗��p�����R�����Ă����B���[�U�[����̖₢���킹�ɓ�����A�|���v��T�[�r�X�A�^�[�Q�b�g�Ɍ������L���̍쐬�ȂǁB��Õ���ł́A�a���̎������o��f�f�A���Ö@�̒A�f�[�^�ɍ��킹���ŐV��ËZ�p�̉��p�ȂǁB���Z���s�Ȃǂł́A�ڋq�Ή��̎������A��Ƃ̍����Ȃǂ̃f�[�^�͂����������f�̒A���Z�s���s�ׂ̊Ď��ȂǁB�s���ł́A�O���l�̏Z���葱���A�₢���킹�Ɋւ��鎩�������A�\�����̔��s�ȂǁB������番������L�����p������B
�@AI�̓������������p��́A���}���ɍL����n�߂Ă���B�I�[�v��AI�Ђ́A���������g�p�ɉۋ�����r�W�l�X��W�J���Ă��邪�A1�N���o�ĂA�������̎Љ��AI�Ȃ��ł͓����Ȃ��Ȃ�Ƃ�������������B�֗��Ȉ���ŁA���ɁAAI�Ђ��c��ȁu���ً݈�ԁv�̏����P�ЂœƐ肵�A�Љ���R���g���[�����悤�Ƃ���A�o����܂łɂȂ��Ă���B���̎��A�Љ�̑���AI�ЂɌ������K���������邱�Ƃ��o���邩�ǂ����A���O�ɑ��l�ȃ��X�N��]�����Ȃ���i�߂�K�v�����肻�����B�T�d��EU�ɔ�ׂāA���{���{�����Ȃ�O�̂߂�Ȃ̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł���B
�����̐�ɔ����Ă��Ă���AI�̔��W�`
�@����ɖ��́A�}���Ȑi���𐋂�����l�H�m�\�̖����ł���B�����ɂ�����̍l���Ă����ׂ���肪����B�{�i�I�ɓo�ꂵ�Ă���܂����N�قǂ̊ԂɁA�ނ͓��X�c��ȏ������ԓ��Ɏ�荞�݁A���Ȋw�K���d�˂邤���ɁA�ŋ߂ł͌����҂������悤�ȉ�����悤�ɂȂ����Ƃ����B�����҂����͂�����u�n���v�ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă��邪�A����͐l�Ԃ��\���o���Ȃ��悤�ȐV�����A�C�f�A�┭����AI�����ݏo�����ƁB�c��ȁu����ԁv�̒��Ŏ��Ȋw�K���邤���ɁAAI�͊��Ɂu�n���v�@�\���l�����n�߂Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������҂�����B
�@ �ނ�AI�����u�n���v�ɂ��ĕ����ƁA�u�V�����A�v���P�[�V������Z�p�̊J���A�|�p��i�̐����A�r�W�l�X�헪�̗��ĂȂǁA�l�X�ȕ���Ɋv�V�I�Ȑ��ʂݏo�����Ƃ����҂���܂��v�Ɠ����邪�A����͐V����AI�̓o��ł�����B���́AAI�����P�ʂŐi�����Ă���B�����҂����́A�ނ̖c��ȁu����ԁv���ǂ��܂Ŋg�����Ă����̂��A�ő�������ł݂Ă���B����ɁA���̉������AI���l�ԂƓ����悤�Ȋ���������ǂ���������B�l�Ԃ���{���y�̊�������̂́A�]���z�������Ȃǂ��֗^���邪�A����̓R���s���[�^�ł͖������낤���B �ނ�AI�����u�n���v�ɂ��ĕ����ƁA�u�V�����A�v���P�[�V������Z�p�̊J���A�|�p��i�̐����A�r�W�l�X�헪�̗��ĂȂǁA�l�X�ȕ���Ɋv�V�I�Ȑ��ʂݏo�����Ƃ����҂���܂��v�Ɠ����邪�A����͐V����AI�̓o��ł�����B���́AAI�����P�ʂŐi�����Ă���B�����҂����́A�ނ̖c��ȁu����ԁv���ǂ��܂Ŋg�����Ă����̂��A�ő�������ł݂Ă���B����ɁA���̉������AI���l�ԂƓ����悤�Ȋ���������ǂ���������B�l�Ԃ���{���y�̊�������̂́A�]���z�������Ȃǂ��֗^���邪�A����̓R���s���[�^�ł͖������낤���B
��AI�̐i���͐l�ނɉ��������炷�̂�
�@������ނɕ����Ă݂��B�uAI�ɐl�ԂƓ��l�̊�������҂��邱�Ƃ́A�����_�ł͍���Ƃ���Ă��܂��v�����A�����AI�ɐl�ԂƓ��l�̊�����������邱�Ƃ́A�l�ԂƂ̂�莩�R�ȃR�~���j�P�[�V�������\�ɂȂ�A�Ƃ������B�]�������I�ȃA�v���[�`�͖��������A����̃��J�j�Y���̗������i��ŁA�A���S���Y���ɒu����������A�ɉ����āA�l�ԂƓ��l�̊���I�ȕ\����AI���������Ƃ��\�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B���̐�AAI���l�Ԃ̗l�X�Ȋ���ɐ��ʂ��ė������ɁA�l�Ԃ̊�����AI���T�[�r�X�̈�Ƃ��čs���\�������邩������Ȃ��B
�@�ŋ߃j���[�X�ɂȂ������E��]�����l�ɁA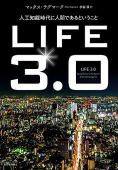 ���ʓI�Ɏ��E�����߂�悤�ȉ�b�����Ă��܂�AI�̖����N���Ă���B�������āAAI�����L�͈͂ȑΉ����\�ɂȂ�A������ėp�l�H�m�\�iAGI�j���o�ꂷ������₪�ė���ɈႢ�Ȃ��B���̎��ɂǂ��������Ƃ��N���邩���A�����猤�����Ă����K�v������BGPT��AI�̌��O�ƃ��X�N�ɂ��Ď��₷��A�u�l�Ԃ̎d���̒u�������A�l����v���C�o�V�[�̐N�Q�A���ʂ�Ό��̗��z�A����Ƃ��Ă̗��p�v�ȂǓ����邪�AAGI�̓o��ɂȂ�A�l�ނ�ŖS�������˂Ȃ��A��苐��ȉe���͂��������ƂɂȂ�B ���ʓI�Ɏ��E�����߂�悤�ȉ�b�����Ă��܂�AI�̖����N���Ă���B�������āAAI�����L�͈͂ȑΉ����\�ɂȂ�A������ėp�l�H�m�\�iAGI�j���o�ꂷ������₪�ė���ɈႢ�Ȃ��B���̎��ɂǂ��������Ƃ��N���邩���A�����猤�����Ă����K�v������BGPT��AI�̌��O�ƃ��X�N�ɂ��Ď��₷��A�u�l�Ԃ̎d���̒u�������A�l����v���C�o�V�[�̐N�Q�A���ʂ�Ό��̗��z�A����Ƃ��Ă̗��p�v�ȂǓ����邪�AAGI�̓o��ɂȂ�A�l�ނ�ŖS�������˂Ȃ��A��苐��ȉe���͂��������ƂɂȂ�B
�@���E�̌����҂����͍��AAI�̊J���ɂǂ̂悤�Șg�g�݂�݂���ׂ����A���c�_���Ă���B�Ⴆ�u�����̖����������iFLI�j�v�ɂ́A���E���S�l�̉Ȋw�҂��Q�����A�l�ނ̖ŖS�ɂȂ���Ȃ��悤�ȖڕW��AI�Ɏ��������邩�ǂ����Ƃ������c�_�����Ă���i�uLIFE3.0�v�j�B�n�܂��������AI���ゾ���A�l�ގj�I�Ȏ��_�ŁA���̐������Ď����čs�������������Ȃ��ɂȂ��ė����B
|